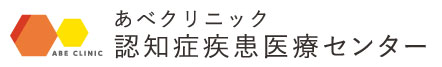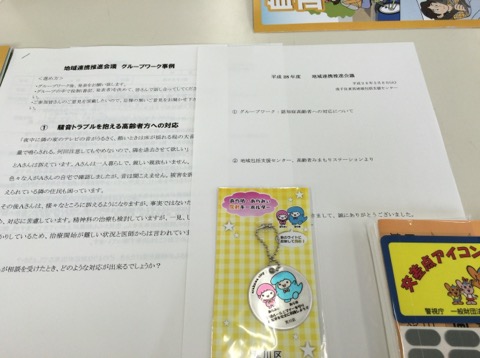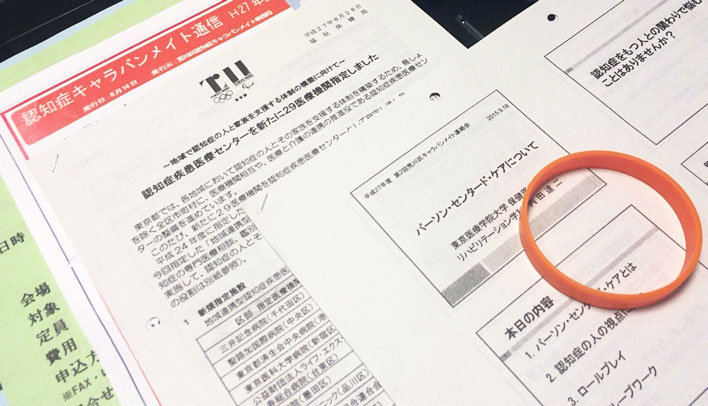平成28年6月15日(水)16:00~17:30
会場:日暮里ひろば館
受講者数:ケアマネージャー 約30名
講義テーマ
「高齢期のメンタルヘルス 〜実践的なストレスケアを知る〜」
講師:医療法人社団 讃友会 あべクリニック
東京都認知症疾患医療センター 副センター長/精神保健福祉士 近藤 康寛
平成28年度第1回東・西日暮里地区ケアマネ懇談会が開催され、当センター相談員が講師を務めました。
ケアマネジャー(専門職)として利用者の心身の健康を考えることは、仕事上として当たり前かもしれません。しかし「専門職自身のストレスケアはしっかり出来ているのだろうか?」そんな視点から、専門職自らのストレスケアを見つめ直すことで、利用者やその介助者のストレスケアのサポートができるように精神科医療機関のノウハウを解説しました。
ストレスを原因とする高齢者の疾患についても実際のケース事例を紹介しながら、疾患を見抜くことの難しさやポイントを情報共有しました。
普段、利用者の心身の健康のことばかり考えているケアマネさん達の「ひと時の癒し」が、明日からの充実した業務の活力になれば、とても嬉しく思います。心から感謝とエールを込めて、講義をさせていただきました。
今後も地域のケアマネージャーの皆さんと、切磋琢磨しながら「やさしい地域づくり」に貢献していきたいと思います。
<受講者のアンケート(25枚回収)の中から一部抜粋してご紹介>
受講者Aさん:うつ病と認知症の見分け方の解説を聞いて、自身の利用者様にも思い当たる方、該当する方がいて、よくわかりました。
受講者Bさん:ストレスが多い仕事なので、少し楽になる方法が再認識出来てよかったです。
受講者Cさん:メリハリのある講義で楽しく受講させていただきました。
受講者Dさん:非常に分かりやすく資料も役に立ちます。自己効力感について知ることができてよかったです。
受講者Eさん:ストレスケアについて理解できました。今後取り入れて行きたいと思います。
受講者Fさん:利用者さん向けの講義が多い中、自分についての事を考えることができました。
受講者Gさん:さすがプロだと感心致しました。
受講者Hさん:わかりやすく受講できました。自分のことを客観的に考えていきたいです。
受講者Iさん:私たちにも当てはまる内容で、わかりやすく参考になりました。
受講者Jさん:認知症とうつ病の違いについて理解できました。
受講者Kさん:自分の事を返りみて、ゆったりとした気分になることができました。勉強というより、時間を忘れることがとてもよかったです。