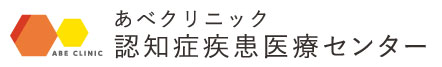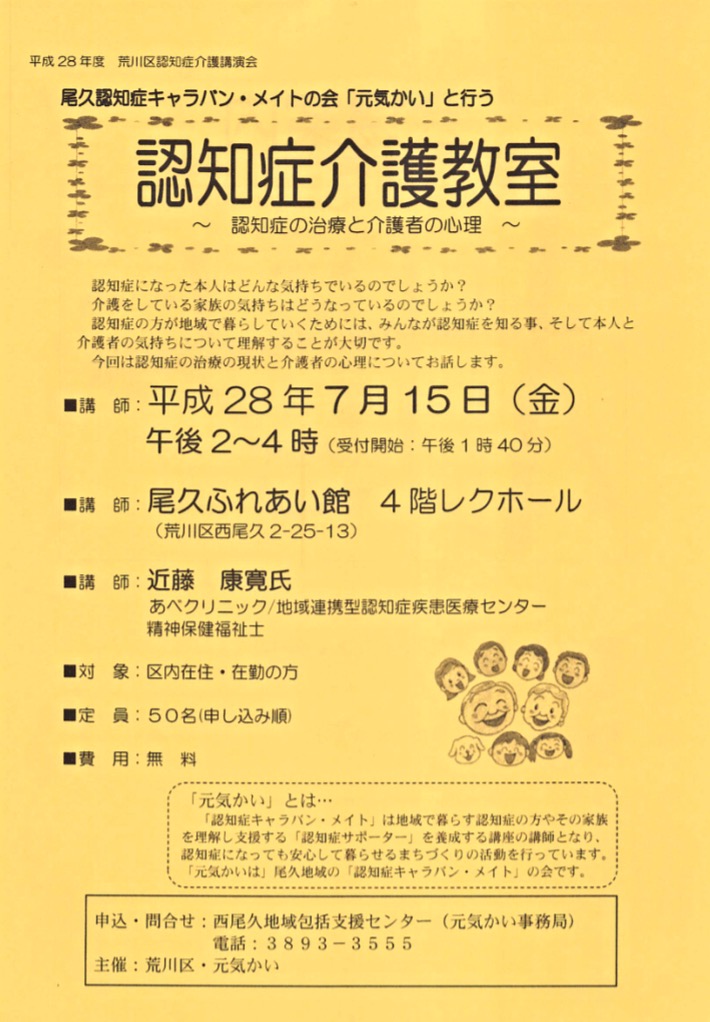かかりつけ医 認知症研修会「荒川区の認知症対策と初期集中支援事業について」
葛飾区かかりつけ医 認知症研修会「荒川区の認知症対策と初期集中支援事業について」
開催日時:平成31年1月29日 19:45~21:45
主催:葛飾区医師会・大内病院
場所:葛飾区医師会館
受講者:葛飾区医師会 医師
講師:あべクリニック 理事長 阿部哲夫(医師)
足立区かかりつけ医 認知症研修会「荒川区の認知症対策と初期集中支援事業について」
開催日時:平成31年3月16日 15:00~17:00
主催:足立区医師会・大内病院
場所:足立区医師会館
受講者:足立区医師会 医師
講師:あべクリニック 理事長 阿部哲夫(医師)
<当日のプログラム>
1.荒川区の認知症対策と
2.初期集中支援事業について
3.荒川区の認知症疾患医療センターが対応した困難ケースについて
阿部先生が認知症疾患医療センターの医師として、葛飾区と足立区のかかりつけ医を対象に、「荒川区の認知症対策と初期集中支援事業について」をテーマに講義を行いました。
受講された医師たちからは、「大変勉強になり、診療に役立ちます」「わかりやすい講義をありがとうございました」との感想をいただきました。今年度は荒川区のかかりつけ医研修会に阿部先生が講師として登壇する予定です。
引き続き、認知症普及啓発活動を推進してまいります。