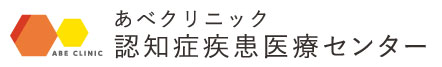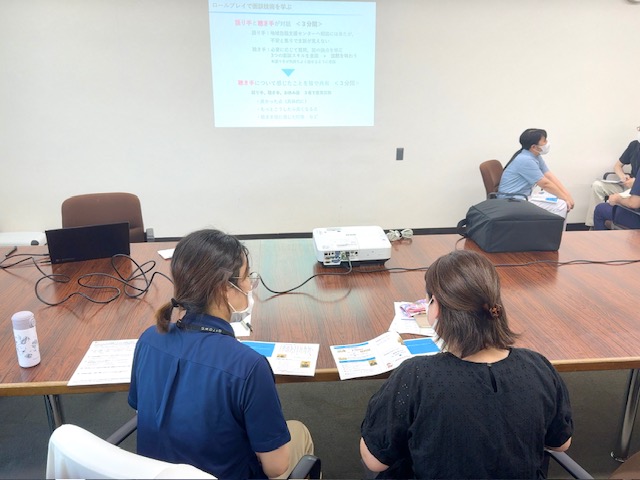<研修の概要>
会の名称 :西日暮里地域包括支援センター スーパーバイズ研修「面談の基本技術」
日時 : 令和7年7月24日 14時~16時
場所 : 荒川区役所 3階 議員待遇者控室(西日暮里地域包括支援センター)
登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛
講義内容:「面談の基本技術」〜「また相談したい」と思われるかかわり方〜
対象者:地域包括支援センター、見守りステーション職員など
主催者:西日暮里地域包括支援センター
受講者の感想から、短時間のロールプレイ(練習)では特に主訴が不明確な場合、本題に入る前に終わってしまったことが分かりました。講師としても研修時間を延ばしたいところですが、理想を言うときりがありません。面談技術の基礎は定期的に短時間のミニロールプレイやペア練習を組み込み、現場で自然に活かせる形にできると、さらに全体的な底上げが期待できます。また、支援では“形”や提案だけではなく、相手の話を整理し背景や感情を言葉にして返すことが大切です。これが「分かってもらえた」という安心感につながります。さらに、感情の反映や非言語対応力も高めたいところです。表情や声のトーン、言葉選びはロールプレイでの相互フィードバックが効果的です。経験年数の違いも強みです。ベテランと新人・中堅をペアにし、気づきを共有し合うことでセンター職員全体のスキルが向上すると思います。
/ 講師 近藤康寛
<受講者の感想>(一部抜粋)
• 研修で心に残ったのは2点です。1つは、たとえサービスにつながらなくても相談や紹介が「橋渡し」になるという気づき。もう1つは、サービスを説明する際に、相手のストーリーに沿った目標を伝えることで具体的なイメージが生まれるという学びです。今後意識して実践します。
• ロールプレイで、意識しすぎると全体像を見失う難しさを実感しました。それでも意識することで成長できると考え、過度にとらわれすぎず技術を高めていきたいです。
• スライドの「チェック項目」「支援職のリスク」は、ほぼ自分に当てはまりました。相談者が話せる“余白”を大切にしようと強く感じました。語り手として体験したことで必要性を実感しました。
• 過去に「伝わっていない」と言われた経験があり、難しさを抱えていました。今回の研修で改めて意識すべき点を学び、緊張しながらも主訴を捉えたいと思います。自然に話せる方を見て、自分もあのようにできるようになりたいと感じました。反映や感情の言語化など基礎技術も磨いていきたいです。
• 経験を重ねると先を決めつけてしまいがちですが、利用者には100通りの対応が必要だと再認識しました。ロールプレイを通じ、語り手の立場を経験することの重要性を学びました。来所者の「話したい」という思いを真摯に受け止め、どう展開するか職員間で考える必要を感じました。異なる立場や考えを学ぶ場として、研修の意義を強く実感しました。