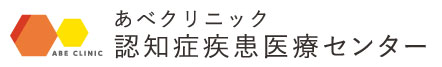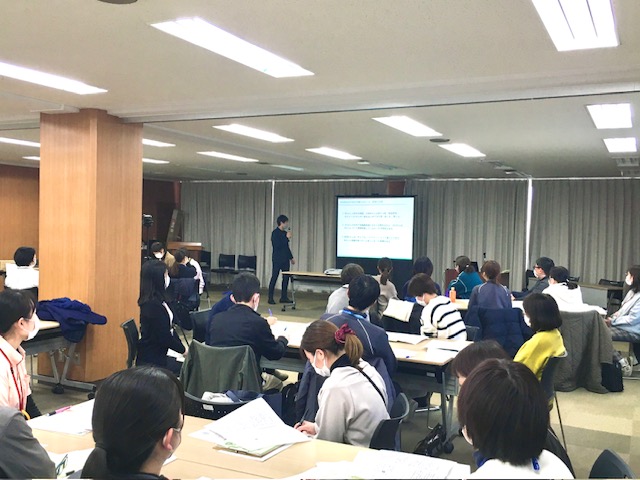<研修の概要>
会の名称 :令和5年地域包括支援センター職員向け(精神保健福祉)研修
日時 : 令和6年1月 11日 13時半~15時半(講義120分)
場所 : 荒川区役所
登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛
講義テーマ:親子の共倒れを防ぐ~精神疾患を抱えた家族介護者の支援~
対象者:荒川区の地域包括支援センター職員、行政職員、行政保健師、行政ケースワーカーなど約50名
主催者:荒川区福祉部高齢者福祉課
<受講者の感想>(一部抜粋)
・事例の経過、結果まで知ることができました。
・現在、精神疾患のある家族が介護をしているケースを担当しているので、お話の内容がとても勉強になりました。
・「問題のある人なんていない」と思うことの大切さを知りました。
・自分では気づけない視点だったので勉強になりました。
・家族歴として捉えて考えるという部分が新鮮でした。
・システム論と対人援助を関連して学ぶことができました。
・課題や問題点だけに視点を置きがちですが、今日の研修で家族療法を学びことができ、必須であることを改めて感じました。
・毎回近藤先生の研修楽しみにしています。目からウロコの内容が多く、自分自身の日々の仕事の振り返りが出来ました。多職種連携の重要性も再確認出来ました。
・前半の内容を踏まえて後半の事例を見ると、「Bさんも一時期ダブルケアラーだったのだな。」と気づき、多面的に家族を見ることの重要さについて学びを得られました。
・家族療法の考え方や、本人や家族の問題を捉えるのではなく、問題ではないと考えることで好循環を生むなど、今までにない考えを学ぶことができ、大変勉強になりました。
・貴重な研修をありがとうございました。支援の経験を積み重ねていくと、良くも悪くも考え方の癖やパターンが出てきますが、本日の「家族療法」「家族の成長と変化」「家族のホメオスタシス」のお話などを通じて、新たな視点や考え方に気づくことができました。自分の支援やマインドのあり方を見つめ直す機会になり、参加してよかったです。気持ちを新たに、明日からのケース対応や認知症支援が更に良いものになるよう、信念を持って継続していきたいと思います。
・対応が難しいケースでは、家族療法を取り入れることが有効な場合もあると知りました。
・家族療法の基本的な考え方について理解できました。12月に入職したばかりで、まだ対象となるケースに出会っていませんが、頭を柔軟にし、誰かや何かの事象を問題とせず包括的に捉えて、多職種と早期から連携し臨みたいと感じました。
・家族をシステムとして捉える家族療法、「問題の人はいない」という考え方を学び、これまでの自分のかかわり方を見直すきっかけになりました。
・家族をシステムとして捉える事が学べました。
・考え方、捉え方の新たな視点に気付かされました。
・家族療法について事例を交えながら学ぶ機会がなかったので、非常に参考になりました。事例検討後、支援の経過を聞き、聴講している身としても感慨深く思いました。本人を支援するには家族は切っても切り離せない関係であるので、今回の講義の内容を自分の中で落とし込んで、今後の支援をしていきたいと思います。
・色々な考え方があって、色々な方向から見ることが出来ることを確認できました。
・家族療法という視点で、支援を考えたことが無かったので、新たな気づきがたくさんありました。
・家族療法について知ることができました。どうしても問題にばかり目が行ってしまいますが、円環的思考を意識し、視野を広げて相談業務をするようにしていきたいと思います。
・興味を持って聞くことができ、分かりやすかったです。
・複雑な多問題を抱える家族の事例が勉強になりました。
・家族療法を支援に取り入れる有効性について学ぶことができました。
・家族療法という言葉を初めて聞きました。家族という文脈を捉えるイメージがつき、普段の相談業務で使うことのできる視点を学びました。
・家族療法の事を知りませんでしたので参考になりました。
・精神医療の切り口からの講義で参考になりました。
・家族療法のライフサイクルから事例ケースを見てみる考えは参考になりました。
・見方、考え方によって支援が変わってくると思いました。
・高齢者世帯を担当していますが、世帯は高齢者だけではありません。家族として、どう対応していくか考えていく必要があり、そのために今回の研修は役に立ったと思います。
・8050や他問題ケースが増えている中で今後どのように対応していけばよいのか、またケアラーの多様化で様々な対応が求められている中でどのような支援をしていけばよいのか、その指標や視点の捉え方の参考になりました。
・家族療法の視点、特に「問題の人なんていない」と本気で思うというのは、実際のケースを考えるととても難しいことだと感じました。いつも問題点を探すことばかりの思考だったように思いました。
・介護者である家族の支援の必要性をより痛感しました。自分自身もワーキングケアラーなので励みになりました。
・私自身、区職員として虐待や共依存といった現状(支援者側から見た問題)をいかに改善するかに焦点を当てて関わっていることが多かったように感じました。家族をシステムとして捉える視点は、措置の権限を持ち、虐待対応の方針決定を担う行政としても非常に重要だと認識しました。
・講座もグループワークもあっという間の2時間でした。グループワークの時間がもう少し長くあれば嬉しかったです。様々な背景を抱えた家族である場合には他機関連携が重要であると感じさせられました。今後、専門職として対応をしていく中で、本人や家族を一概に決めつけることがないよう対応をしていきたいと、改めて思いました。家族療法の話はゴールキーパーの例えがとてもわかりやすかったです。今回の事例のような場合であると、重大な事柄が起きる前に世帯分離の判断をせざるを得ないと思いました。しかし、その判断を、家族を悪いと決めつけて行うべきではないのだと感じました。また、一概に困難な虐待案件であるからとすぐに『世帯分離しかない』と判断を下すのも違うのだと学びになりました。何が家族の中で悪循環を生んでいるのか、見極める目も必要だと思いました。とても良い事例で勉強になりました。
・オンラインより対面式の方が、近藤さんや他職員さんの熱量を感じられ、自分のモチベーションにもつながると感じたので、状況が許せば、今後も対面式を希望します。
・地域包括支援センターは、基本的には65歳以上の方への対応を行うため、家族にも支援が必要な場合は、健康推進課の保健師さんと一緒に関われれば、スムーズに支援が進むこともあるのではないかと思いました。
・医療職の考え方を学び、勉強になりました。
・「何が問題なのか?」「誰が問題なのか?」という考え方を持たずに話を聞き支援していきたいと思いました。
・私はケースに対して何が問題かとばかり考えがちです。特定の一人だけにとらわれず、家族をライフサイクルの段階で見ることや、家族間の相互作用を意識してお話しできるよう心がけたいと思いました。ありがとうございました。
・家族療法の全てを理解した訳ではない為、断定すべきでないとは思うのですが、緊急性の高い時は問題解決思考、信頼関係の構築や家族を含めた情報収集、対応方法の検討時には家族療法の思考に軸をおくなど、緊急性の高さや時期、タイミングによって家族療法や問題解決思考を使い分けて対応していくのが良いのではと個人的には感じました。
・学んだ内容を現場で生かしていきたいと思います。
・臨床心理学で考える取組は勉強になりました。自身でも勉強したいと思いました。
・問題が世帯の高齢者だけではなく、他の年代にもある場合、他の機関との連携が必要になりますが、誰がまとめ役になっていくかがとても大切になっていくと思います。年齢に関係なく世帯全体を見ていくファミリーサポーターのような役割があるといいと思いました。